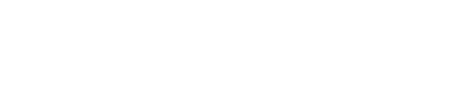「鞴祭(ふいごまつり)」について調べている。
旧暦11月8日に稲荷社で行われる鍛冶屋の祭りだ。
そのために読んだ本からメモ。
支倉清+伊藤時彦 著『お稲荷様って、神様?仏様?
』
わが国の神仏の中で、最も多く祀られているのは稲荷である。
稲荷は、その名の示す通り、もともとは農耕の神として信仰された。
古代の人々は、すべての穀物には霊力(穀霊)が宿ると考え、稲には稲の霊力・稲魂(いなだま)が宿ると考えた。稲魂とは、稲に宿ってその生育や豊作・不作を左右する霊力である。
古い文献には「是(これ)は稲の霊(みたま)なり、俗の詞(ことば)、宇賀能美多麻」とある。すなわち、稲魂=ウカノミタマ=田の神=稲荷なのである。
稲荷社の総本宮が京都の伏見大社であるのに、京都やその周辺に稲荷社は少ない。多いのは関東である。このことをどう考えるか。
稲荷社には京都の伏見稲荷から勧請された系統と、それとは無関係に田の神などがもとになって成立した系統とがある。江戸にも伏見稲荷が勧請された例は少なくないが、そのほとんどは伏見稲荷とは無関係に成立したものである。
江戸のまちが一年の中で最も活気づくのは初午祭(はつうまさい)のときである。 この祭りは旧暦二月の最初の午の日に行われる。そのいわれは、稲荷社の総本宮、京都の伏見稲荷大社の神が稲荷山に初めて降り立ったのが、和銅4年(711年)2月11日で、その日が二月の最初の午の日にあたった、という伝承による。
ここには初午祭本来の豊作祈願という要素はほとんどみられない。稲荷の祭りとはいうものの、都市に暮らす人びとの娯楽的年中行事へと変化したのである。
寺子屋に入ってはじめに習う字が「いろは」の「い」の字であるが、「いなり」の「い」の字でもあるので、縁起を担いで初午に入学するようになったともいわれている。
寺子屋は本来いつでも入門することができたが、江戸では初午の次期に入門する子供が多かった。旧暦の二月初午は、現在の三月頃にあたり気候が春めいてくる頃である。農家では田植えに向けて田起こしなどの準備が始まる。山から「田の神」(稲荷神)がおりてくるこの次期に、江戸の寺子屋でも新年度が始まった。
新年度が4月なのはこの辺にも理由があるのか?
鞴祭
人口密集地の江戸で伝染病とともに恐れられたのは火事である。江戸の人びとは土地の守護神である稲荷に「火防せ」を祈願した。十一月八日に行われる鞴祭はもともとは京都伏見稲荷大社の火焚祭(ひたきさい)であった。この火焚祭が稲荷信仰を持つ鍛冶屋や鋳物師の間で鞴祭りと呼ばれるようになったのだが、それが江戸にも伝わった。ところが、三崎稲荷神社の氏子には鍛冶屋も鋳物師もいない。そこで、神社自ら蜜柑をまき、神楽を催し、「お火焚き」を行って人びとを集め、火防せの守札を販売したのであった。
旧暦で十一月八日といえば、寒さが一段と厳しくなる頃である。木造の密集した住宅地に住む江戸の人びとにとって、現代のわれわれには想像もできないほど火災は恐ろしいものだったに違いない。当時の人びとにとって火災から命や財産を守るためには稲荷の力が不可欠だったのである。
鞴祭は鍛冶屋や鋳物師など火を使う職人の祭として全国各地で行われている。伏見稲荷大社の火焚祭は五穀豊穣を感謝する祭典で、本来の「田の神」に感謝する祭である。これが鍛冶屋や鋳物師の祭として全国に広まるにはもう一段階何かきっかけがあったように思う。
どこかほんの一部の稲荷社で伏見稲荷大社の火焚祭を模して鍛冶屋職人が行っていた鞴祭を江戸に増えた稲荷社が防火の意味で取り入れ、それを全国各地から来た行商人が地元の鍛冶屋など職人に伝え広まったのではないかと想像できる。情報の中心地、江戸で流行っている出来事だから全国に広まったというわけだ。
上記の三崎神社の様子は「絵本江戸風俗往来」に依るものらしい。この本は幕末生れの画家・菊池貴一郎(1849-1925)が明治36年(1903年)に刊行した画集だそうだ。少なくとも江戸の後期~幕末頃には鞴祭が広まっていたことが考えられる。
また紀伊國屋文左衛門が鞴祭用の蜜柑を紀州から江戸に運んだという話があるが、これは文左衛門が20代の頃らしいので、本当なら1690年代である。しかし江戸時代が始まって100年以内の頃に稲荷社が多く建てられたのか、またそれらで鞴祭が行われていたのかは気になるところである。
この本『お稲荷様って、神様?仏様?』には他にもダキニ天、地蔵、観音、不動など気になる話が多く掲載されていて興味深い。