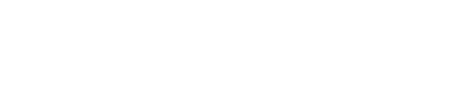松前健 編 『稲荷明神』
この本は稲荷明神、稲荷信仰について記されている。興味深い内容が多々あるが、鞴祭について抜出し考察する。
京都の伏見稲荷大社で執り行われている〝特殊神事〟(その神社固有の神事)に火焚祭(ひたき、火焼神事、冬御祭、冬祭、冬期御祭、冬期神祭、吹革祭(ふいかう)などと称した)がある。
(伏見稲荷大社の)火焚神事および火焼次第は、そのポイントに〝大祓詞〟があり、かつ焚き上げられた火の霊力に除災招福を期待するのをみてとることができる。これは先に示した〝ひたき=神前火焚の儀〟にうかがえる農耕儀礼から、展開を示すものと考えられている。
これについて、鍛冶職に携わる人々の、火・炎に対する畏怖の念とともに、それをたのみとする信仰が、やがて〝ふいご祭り〟として確立し、ついには伏見の稲荷社の〝ひたき=冬御祭〟と同一化していくが、その前提として、謡曲『小鍛冶』の存在は注目に値する。『小鍛冶』の成立は天正12年(1548年)以前にさかのぼるとされ、あらすじは、一条院に御剣打つべしと命ぜられた三条小鍛冶宗近が、相鎚にふさわしい者が得られるよう祈願のため稲荷神社へ参詣する…
伏見稲荷大社の火焚祭はあくまでも農耕の儀礼だった。しかし火を焚く神事から農耕以外にも関連する鈎となる。
ここで火焚祭の別名が「冬御祭」というのが面白い。「ふゆごまつり」という語呂に「ふいごまつり」が重なってきたというのは有力な説となり得るのではないかと思う。なぜ鞴なのか。鍛冶屋の祭りなら鎚ではいけないのかという疑問に明解に解釈を与える。
『小鍛冶』には鍛冶屋と稲荷神社との関係も謳われているが、それが前提にあったとしても「ふゆごまつり」≒「ふいごまつり」という音が結びつけたのではないかと思う。
時代的には享保17年(1732年)に伏見稲荷社で「吹革祭」または「ふいご祭」が行われたという文献があるという。
11月8日の祭りを、農耕者が祈願する〝ひたき〟祭りと称される一方において、工業者が祈願する〝ふいご〟祭りと明確に別の名称で表現されている。これは、稲荷明神にもっぱら年穀豊穣を祈願していたところに種々の折りが積み重ねられ、ついには自分の生業の繁栄を願うにいたるという信仰の拡大展開が示されているように思う。
農業以外の人々が祈願するようになったとはいえ、なぜ鍛冶職人の鞴祭なのかといえば「火・炎」と「ふゆご」の音であろう。鈎に最も引っ掛かったわけだ。
火焚きは、古い時代の人々が、冬至のころ、神の働きのしるし、あるいは依代と考えた稲藁に火を点じ、そこから立ち昇る煙とともに神を元の御座(みくら)に送り、来る年の日照の復活=神威の甦りを願う民俗行事(鎮魂儀礼)が形を整えて継承されたもの、との考え方が一般的のようである。
しかし、伏見稲荷大社の火焚きが、恒例の祭事として古くから伝承されたものであるか否か、しかも神供をともなう祭典としてのそれであったかというと、社内に伝来する史料を見る限りでは、即座に応とはいいがたい。
火焚きが古代の信仰によってもたらされたものであるなら古くからの神事であるが、史料ではそう古くはないとのことだ。火焚き自体は古くから行われていたかも知れないが、祭典としては慶安4年(1651年)ころではないかということらしい。
1651年頃に京都の伏見稲荷大社で火焚祭が始まり、80年後の1732年頃までに鞴祭が行われるようになった。
丁度4代将軍徳川家綱~8代将軍吉宗の頃である。戦乱の世が過去のものになり、江戸の都市形成が進み栄えた時代である。短い期間に見えるが稲荷社や鞴祭が江戸に広まったという可能性は十分ある。(1690年代の紀伊國屋文左衛門が鞴祭用の蜜柑を運んで大儲けするほど広まっていたかは疑問である。